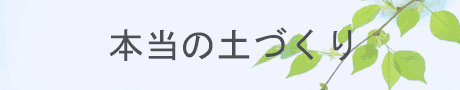
数千年前、農耕文化が始まってきてからコツコツ積み上げてきた生産効率を、昭和のたった数十年で倍近く高めることに成功しました。そのお蔭で一反当たりの収量は、江戸以前とは比較にならないほど豊かになりました。しかしその反面、土壌にかかる負荷は非常に大きくなり、搾取した以上を還元できない圃場は、近年どんどんやせ細ってきています。そのため多くの方が土づくりに関心を持たれるようになりましたが、実際何を目的に何をすれば良いか分からない方も多いと思います。ここでは簡単な土づくりの方法を説明させて頂きたいと思います
先ず土づくりの目的ですが、結果として固相、液相、気相の割合が4:3:3となるような団粒構造を作らなければなりません。この構造比になると、保肥性が高まり、微生物が活動しやすい水分量となり、また水捌けが良いのに保水性もあるという土壌になると言われています。ただここで一番重要なのは、この団粒構造を、腐植によって作りだすことにあります。
腐植にはキレート構造があり、物と物をつなぐ性質があります。また、微生物の増殖しやすい環境を作りだし、健全な土壌を育むことによって、毎年微生物の死骸から、多くのアミノ酸を含んだ土壌を作りだします。その量は健全な土壌であれば、毎年1.2トンもの量になります。また、微生物自体が産出する物質でも、土壌を団粒化します。
そして腐植は多くのフェノールを含むため、植物の体を構成するうえでも重要な物質となります。さらに腐植のもつ力はそれだけではありません。
先ほど、団粒構造を作る上でのメリットに、保肥性が出てきましたが、この保肥性を作りだす、最も効率の良い物質が腐植になります。保肥力とは基本CECといって、カチオン・エクスチェンジ・キャパシティーと言い、カチオンはプラスイオン、エクスチェンジは交換、キャパシティーは容量なので、陽イオン交換容量となります。陽イオンを捕まえる力なので、陰イオンをどれだけ持っているかとなるのですが、腐植はこの陰イオンを非常に多く持っています。土で20程度、砂地ではほとんど陰イオンが無く0から1、肥料などを吸着する為に使用されている、バーミュキュライトやゼオライトなどで、100から150ですが、腐植は600から800の陰イオンを保持しています。(単位me/100g)300程度と言われている学者もおられますが、それでも断トツに陰イオンを持つことになります。
アンモニアやカリウム、カルシウムやマグネシウム、水素など多くが陽イオンですが、例えばアンモニアを陰イオンによって吸着し保持出来ると、イオン化をさせずに急激に硝酸化するのを防ぎます。硝酸化しなければ植物は吸収出来ませんので、窒素の片効きを防ぎ、多量の亜硝酸ガスなどの発生を抑える事も出来ます。カルシウムもPHを急激に上げることもありませんし、植物が根酸によって養分を吸収し易くなります。
しかし、植物の外壁を構成する物質はセルロース、へミセルロース、リグニン、ペクチンです。その中のリグニンはフェノールという物質で成り立っています。腐植もフェノールからなり、植物は多くの腐植を吸収し成長していきますので、これらの物質を新たに投入できなければ、当然土壌から枯渇していくことになります。堆肥を施さない作付けは、何千年何万年、それ以上の自然が培ってきた養分を奪うだけ奪って返さない、略奪式農法といえます。
ですから、土づくりをしない農地は、年々連作をしていく上で、やせ細っていくのです。
適切な堆肥を投入することは、それほど重要なことなのです。
では土づくりをするために何を投入すれば良いか。その為には、上述した腐植、粘土質(シルト含む)、微生物が必要になります。粘土質と微生物を横に置いてズバリ言うならば、お勧めはバーク堆肥になります。腐植はフェノールとカルボン酸から出来ています。これがさらに固まって大きな形になったものがリグニンです。そしてリグニンとは木質に多く含まれるものです。効率よく腐植を増やしていくのには、バーク堆肥が一番理に適っている事になります。
しかし、バークは危険と考えておられる方も多いでしょう。実際バーク堆肥を使用し大変な目に合われた方も沢山いらっしゃいます。ですが、バーク堆肥が危険なのではありません。炭素率の高い未熟なバーク堆肥を投入することが危険なのです。
土壌の平均炭素率は、13から14と言われています。仮に炭素率25のバーク堆肥を入れると、この値近くまで同化していきます。木質が分解するときに、大量のリグニン酸を放出するので、リグニン濃度障害が起こります。いわゆる連作障害を、自らの手で起こす事となるのです。
リグニンが何故腐植化するまで植物にとって毒となるかは、多分これらの物質が分解する工程に合わせ、生物が存在しているからだと私は考えます。植物の外壁を構成する腐植が次から次へと消費されれば、巨木など時間のかかるものは育っていきません。ですから、ある程度の養分を蓄積させるために、毒として機能し、またその間にエネルギー消費の大きな植物が育たないように、フザリウムやラルストニア・ソラナケアラムなどの病原性の菌が活躍するのだと考えています。実際、植物の生産する他感作物質の中には、後の世代を存続させるため、防衛反応で自らを枯らす毒を生成する事もあります。
これらから、リグニンが堆積する状態は、フザリウムやラルストニア属には、エサとなり都合よく、植物には都合が悪い状態になります。となると答えは簡単で、植物にとって都合の良い状態、土壌の炭素率に近い状態まで、バーク堆肥の炭素率を発酵によって下げたものを投入すれば、腐植の多い植物にとって都合の良い状態を、初めから持っていく事が出来るというわけです。
☆腐植の役割
団粒構造を作る。有効微生物を増やす。保肥性を高め、養分の過剰などから植物を守る。植物自体のエサとなり、外壁などを構成する物質に変わる
☆微生物の役割
団粒構造を作る。有害微生物から植物を守る。死骸はアミノ酸など肥沃な土壌となり、植物に吸収される。有機物の分解を担い、連作障害を緩和させる等
そして、以上の事柄から、木質の入らない、または少ない堆肥は肥料でしかありません。
セルロースの多いワラやケイントップなども、一時的な物理構造の改善や、微生物のエサとしては有用ですが、βグルカンという糖で出来ているため、ほとんど土としては残りません。
熟成した堆肥は残りカスだと言われる方がいらっしゃいますが、それはし尿やワラなど、土として残らないものを指しているのでしょう。木質が完全に自然界で分解すれば、それこそが難分解性化合物である腐植ですから、土壌で最も必要な物質のひとつになります。
また、最近では生のものをわざと投入する方法もありますが、それは崩壊途中に、腐植酸の一つであるフルボ酸が大量に放出されるため、根がよく伸び、放出される養分を餌として、微生物が育まれるからなのですが、そもそも健全な土壌であれば、自然と常在菌は繁殖しますし、上記で述べたフザリウムもラルストニア属なども分解菌なので増殖するリスクがあります。特にこれらはリグニンを好むため、注意が必要です。
さらにフルボ酸は安定しにくい分、酸が強く、細根を焼くことで知られています。
細根が焼かれれば、そこから様々な土壌病の罹患率も上がりますし、細根はリン酸の肥効に大きく係わりますので、ADPやAMPといったリン酸化合物の生産量も落ちてしまいます。AMPやADPが少なくなれば、光合成で取り入れられるエネルギー量も減少します。
当然根域が減れば、その分根の範囲でほとんど行う、GS/GOGATサイクルの範囲も減少しますので、アミノ酸やタンパク質の合成量も減ります。なので、ある程度までならかまいませんが、一定の品質以上のものを作りたいのであれば、お勧めできません。
生のものを投入される場合は、堆肥としてではなく、肥料として考える方が、妥当ではないでしょうか。
結論
土を作るには、炭素率の低い熟成した木質系の多い堆肥を、消費される腐植分以上に投入する。
